A book is a dream that you hold in your hand.
本とは、あなたが手に抱える夢である。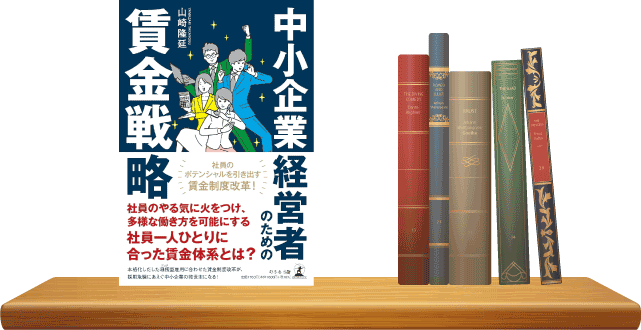
目的地というものは決して場所ではなく、
物事の新しい見方である。
時代が変われば、経営の仕方も変わる。
しかし変えてはいけないこともあると思う。変化が早い時代でも、企業の根幹である「人」に対しては、いつの時代も思慮深く、お互い様であることが理想である。
そんな理想な景色が見られるように何をしていくことが望ましいかを常に考えていかなくてはならない。
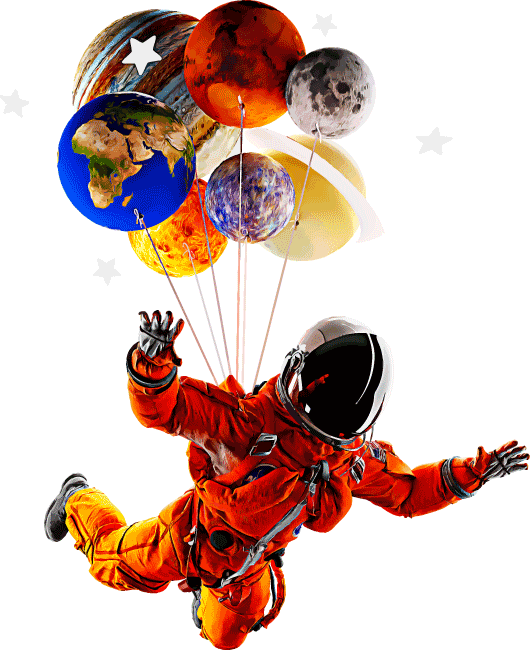
あなたの見たい景色をクリックして旅に出よう。











